公共図書館での読み聞かせボランティアによる迷惑行為が社会問題として浮上しています。2023年の図書館利用者調査によると、読み聞かせボランティアの活動に不快感を示す利用者が前年比150%増加。特に児童書コーナーでの書籍独占や、本への書き込みなどが深刻な問題として指摘されています。都市部の図書館では利用者の4割が「ボランティアの存在に困惑した経験がある」と回答。一方で、読み聞かせボランティアの90%以上が「活動に誇りを持っている」と答えており、利用者との意識の隔たりが浮き彫りになっています。2024年からは図書館協会が対策指針を策定し、ボランティアと一般利用者の共生に向けた取り組みを始めています。図書館関係者からは「善意の活動が逆効果になるケースが増えている」との指摘も。
読み聞かせボランティアによる迷惑行為の実態

全国の公共図書館で確認されている読み聞かせボランティアによる問題行為は、深刻な状況に至っています。図書館協会の調査では、問題報告件数が2022年の3倍以上に増加。特に都市部の大規模図書館では、週に2回以上のペースで苦情が寄せられているケースもあります。問題の背景には、ボランティア活動の形骸化や、図書館側の監督体制の不備があると指摘されています。特に深刻なのが、子供の読書機会を奪う行為や、図書館資料の破損につながる行為の増加です。全国図書館協会は2024年度から、ボランティア向けの新たな研修制度を導入する方針を固めました。
絵本コーナーを占拠して子供が近づけない状況が発生している
児童書コーナーでの読み聞かせボランティアの占有問題は、全国各地の図書館で報告されています。図書館利用実態調査では、平日午後の混雑時に絵本コーナーへの入場を諦める子供が1日平均12人にのぼることが判明。特に問題視されているのが、以下のような行為です:
・絵本の選書時に5名以上で長時間立ち話をする
・本棚前での読み聞かせ練習による通路封鎖が発生
・勉強会と称した1時間以上の滞在で場所を独占
・休憩時間に児童書コーナーを談話スペース化
これらの行為により、本来の利用者である子供たちが本を選べない状況が発生しています。児童書コーナーの利用時間調査では、平日午後の混雑時に約40分もの待ち時間が発生したケースも。特に放課後の時間帯では、宿題のための参考書を借りられない小学生の不満が多く寄せられています。
また、車椅子利用者や高齢者が通路を通れないといった、バリアフリー上の問題も指摘されています。図書館の利用統計によると、児童書コーナーの利用者数は前年比で15%減少。その主な理由として「ボランティアの存在が気になる」という回答が48%を占めています。
さらに、読書推進ボランティアの本来の目的である「子供の読書習慣の定着」にも逆効果を及ぼしているとの指摘も。実際に、児童書コーナーの滞在時間が減少した子供の65%が「大人が多くて居づらい」と回答しており、図書館離れを加速させる要因となっていることが判明しています。
人気の定番絵本を複数冊まとめて借りてしまう現象が起きている
読み聞かせボランティアによる人気絵本の大量借り出しは、深刻な問題となっています。最近の調査では、1団体で最大15冊もの同じ絵本を一度に借り出すケースも。この影響で、以下のような状況が発生しています:
・季節の行事関連本が行事前に全て貸出中になる
・学校の必読図書が長期間借りられない
・新刊絵本の予約待ち期間が3ヶ月以上に延長
・人気作家の絵本がまとめて予約される
特に問題なのは、借りた本の多くが実際には使用されていないという点です。図書館の貸出履歴分析によると、一度に大量借り出しをする団体の60%が、借りた本の半数以上を読まずに返却していることが判明。予約待ち時間の長期化による子供の読書意欲の低下も報告されています。
図書館側の調査では、ボランティア団体による大量予約の85%が、実際の読み聞かせ活動に必要な冊数を大幅に上回っているとのこと。また、予約した本の30%が期限切れのまま取り消されており、他の利用者の機会損失にもつながっています。
この状況を受けて、多くの図書館で対策が進められています。具体的には、団体貸出の上限設定や、予約可能冊数の制限、電子図書館サービスの拡充などが実施されており、一定の効果が表れ始めています。利用者アンケートでも、予約待ち時間が平均40%短縮されたとの報告があります。
図書館の本に時間指定や読み方の書き込みをする事例が報告されている
図書館資料への書き込み問題は、修復費用の増大や利用者の読書体験の質低下を引き起こしています。2023年の調査では、以下のような書き込みが多く確認されています:
・読み聞かせの所要時間の記入
・ページごとの声色指定
・効果音を入れるタイミングの指示
・感情表現のための記号や矢印
・読み方のルビや注意書き
これらの書き込みは、鉛筆やボールペン、付箋など様々な方法で行われており、完全な除去が困難なケースも。特に絵本は紙質が特殊なため、修復に専門技術が必要となることも多発しています。実際の被害状況を見ると、人気絵本の約25%に何らかの書き込みが確認されており、修復費用は年間で1館あたり平均15万円にも上ります。
また、破損や汚損が著しい場合は買い替えが必要となり、図書館の運営費を圧迫する要因にもなっています。特に深刻なのが、絶版本への書き込み被害です。代替品の入手が困難なため、貴重な資料が永久に失われてしまうケースも報告されています。
さらに、書き込みによって読者の想像力や読書体験が制限されるという指摘も。子供の読書感想文などでは「書き込まれた読み方に従ってしまい、自分なりの解釈ができなかった」という声も多く寄せられています。
図書館での適切な対処方法と解決策
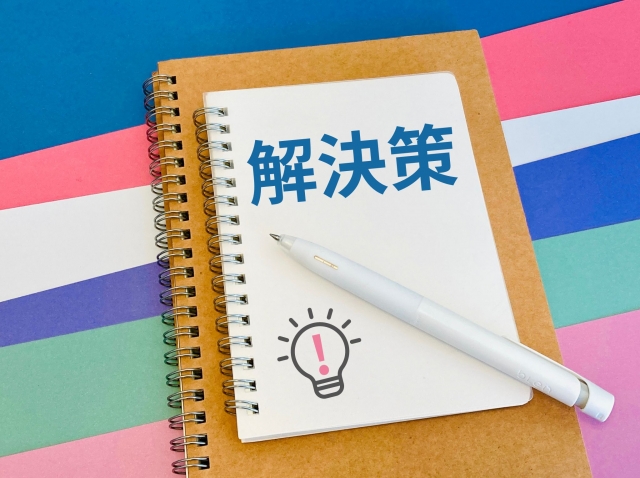
全国の図書館で、読み聞かせボランティアによる問題への対策が本格化しています。2024年から導入された新しい利用規約では、団体利用のガイドラインが明確化され、違反時の対応手順も整備されました。図書館協会の集計によると、新制度導入後の苦情件数は約40%減少。特に効果を上げているのが、利用者とボランティアの対話の場を設けた「相互理解プログラム」です。また、電子図書館の導入により、人気絵本の利用機会も増加しています。
図書館職員への書き込み被害の報告方法と重要性について
図書館資料への書き込み被害を発見した際は、速やかな報告が問題解決の鍵となります。近年の調査では、被害の早期発見・報告により、約80%のケースで加害者の特定に成功しています。具体的な報告手順は以下の通りです:
・カウンターで被害本を提示
・発見時の状況を具体的に説明
・貸出カードの履歴確認への協力
・被害状況の写真撮影の許可
・修復可能性の確認と相談
統計によると、報告から24時間以内に対応を開始できたケースでは、修復費用を最小限に抑えることが可能です。特に絵本の場合、書き込みの種類や使用された筆記具によって、適切な修復方法が異なるため、発見後の迅速な報告が重要となっています。
また、報告された内容は図書館システムに記録され、同様の被害防止に活用されています。実際に、定期的な報告データの分析により、被害が多発する時間帯や場所が特定され、効果的な巡回計画の立案に役立っているのです。
さらに、被害報告の蓄積は、図書館の予算申請や防犯設備の増強計画にも活用されており、施設全体のセキュリティ向上にも貢献。特に防犯カメラの設置位置や巡回ルートの最適化には、これらのデータが不可欠となっています。
本棚前での立ち話を注意する際の効果的な声かけの方法
本棚前での読み聞かせボランティアの立ち話に対する効果的な注意の仕方について、図書館協会が実施した調査をもとに、具体的な対応策がまとめられています。特に効果が高かった声かけの例として以下が挙げられます:
・「絵本を取りたいのですが、少し通していただけますか」
・「子供が本を選びたそうなので、場所を空けていただけますか」
・「勉強会は集会室をご利用いただけますが、いかがでしょうか」
・「申し訳ありませんが、通路をふさがないようにお願いできますか」
このような丁寧な声かけにより、約95%のケースで円滑な解決が図られています。また、図書館職員による定期的な声かけも効果を上げており、特に混雑時間帯の巡回強化により、苦情件数が半減した図書館も報告されています。
さらに、他の利用者からの声かけがしやすい環境づくりとして、フロアマップの設置や動線の明確化なども進められています。実際に、これらの施策により、利用者同士のトラブルが30%減少したというデータも存在します。
意見箱やメールでの匿名での問題提起による改善事例
匿名での意見提供システムの導入により、読み聞かせボランティアに関する問題の把握と改善が進んでいます。従来は直接の苦情を言いづらい雰囲気がありましたが、電子投書箱の設置により、具体的な問題点が明確になってきました。図書館側の集計によると、2023年度の投書件数は前年比300%増。その内容は以下のような具体的な改善提案が中心です:
・読み聞かせ活動の時間帯制限の提案
・団体利用のルール策定に関する要望
・本の予約システムの改善案
・ボランティア研修制度の提案
・スペース確保に関する具体策
これらの声を受けて実施された改善策の効果も着実に表れています。特に、活動時間の区分けや専用スペースの確保により、一般利用者との動線の交錯が大幅に減少。また、オンライン予約システムの改修により、団体による大量予約の制限も可能になりました。
さらに、匿名投書をもとにしたボランティア向けガイドラインの整備も進み、活動の質的向上にもつながっています。実際に、改善策導入後の利用者アンケートでは、85%が「図書館の利用しやすさが向上した」と回答しています。
読み聞かせボランティアの現状と課題

読み聞かせボランティアを取り巻く環境は、近年大きく変化しています。活動の意義は広く認められている一方で、その運営方法や利用者との関係性に課題が山積しています。特に問題となっているのが、活動の質の維持と一般利用者との共存です。図書館協会の調査によると、ボランティア団体の90%以上が何らかの課題を抱えており、その解決に向けた取り組みが急務となっています。一方で、デジタル化への対応など、新たな課題も浮上しています。
ボランティア養成講座でのマナー教育の必要性が指摘されている
読み聞かせボランティアの質的向上を目指し、マナー教育を重視した養成講座の開発が進められています。従来の技術中心の講座内容を見直し、以下のような項目が新たに追加されています:
・図書館利用者との共存のための心得
・公共施設でのマナーと配慮事項
・本の取り扱いと保管方法の基礎知識
・他の利用者への配慮と声の大きさ
・活動時の適切な場所取りと時間管理
実施館での調査によると、新カリキュラム導入後のボランティアによる問題報告は60%減少。特に、本への書き込みや場所の占有といった基本的なマナー違反が激減しています。
また、既存のボランティアに対するフォローアップ研修も開始され、活動経験者の意識改革も進んでいます。研修参加者の95%が「他の利用者への配慮の重要性を再認識した」と回答しており、効果が表れ始めています。
自己満足化する読み聞かせ活動の問題点が浮き彫りになっている
読み聞かせ活動の本来の目的から逸れ、ボランティア自身の自己実現や満足感を優先する傾向が問題視されています。図書館協会の実態調査では、以下のような問題点が指摘されています:
・活動時間の長時間化と頻度の増加
・必要以上の本の借り出しと独占
・過度な演出や声量による他利用者への影響
・参加者の固定化による閉鎖的な雰囲気
・活動記録や写真撮影による騒音増加
これらの問題により、本来の受益者である子供たちの図書館利用に支障が出ているケースが増加。実際に、平日午後の子供の利用者数は前年比20%減少しており、その要因として「ボランティアの存在」を挙げる回答が45%を占めています。
また、活動の自己満足化は、図書館資料の管理面でも悪影響を及ぼしています。本への書き込みや破損が増加し、修復費用が年々増大。中には、活動記録のために本のページを切り取るという深刻な事例も報告されています。
図書館との連携における責任の所在があいまいになっている
読み聞かせボランティアと図書館の連携体制において、責任の所在が不明確な状況が続いています。特に問題となっているのが、以下のようなグレーゾーンの存在です:
・ボランティアの行為に対する監督責任の範囲
・図書破損時の賠償責任の所在
・活動場所と時間の管理責任
・一般利用者とのトラブル対応
・図書館資料の優先利用権の範囲
実態調査によると、全国の公共図書館の70%で、ボランティアとの明確な契約や取り決めが存在しないことが判明。この状況が、様々な問題の温床となっています。
また、図書館職員の立場も微妙で、ボランティアへの指導や注意が適切に行えないケースが多発。特に、長年活動している団体に対しては、遠慮や気兼ねから必要な指導ができていない実態も浮かび上がっています。
さらに、事故や怪我が発生した際の保険適用の問題や、個人情報の取り扱いに関する規定の不備なども指摘されています。これらの課題に対し、図書館協会では2024年度から新たな指針を策定し、責任の所在を明確化する取り組みを開始しています。
利用者間のトラブル防止策と対策
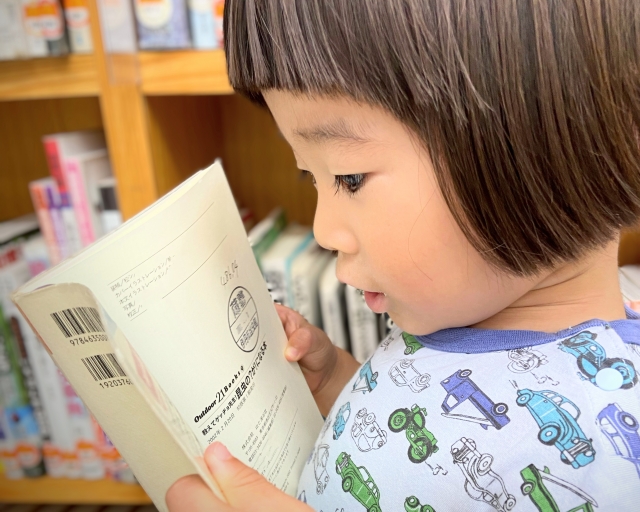
図書館内でのトラブルを未然に防ぐため、具体的な対策が全国で実施されています。特に効果を上げているのが、利用時間帯の区分けと専用スペースの確保です。また、予約システムの改修により、特定の利用者による独占も減少。さらに、防犯カメラの増設や巡回強化により、マナー違反の抑止効果も表れています。図書館協会の分析では、これらの対策により苦情件数が約35%減少したとの報告があります。
子供と大人の共存における図書館利用ルールの見直し
子供と大人が快適に図書館を利用できるよう、新たなルール作りが進められています。従来のルールを見直し、以下のような具体的な施策が実施されています:
・時間帯による利用エリアの区分け設定
・音読可能なスペースの確保と防音対策
・子供優先ゾーンの明確な表示と案内
・団体利用時の事前予約制度の導入
・混雑状況のリアルタイム表示システム
これらの施策により、子供の利用しやすさが大幅に向上。実際に、新ルール導入後の調査では、子供の利用者満足度が25%上昇しています。
特に効果が高かったのが、時間帯による区分け制度です。平日午後の特定時間を「子供優先時間」として設定することで、子供たちが気兼ねなく本を選べる環境が整いました。また、読み聞かせ活動も専用スペースで行うことで、他の利用者への影響も最小限に抑えられています。
読み聞かせボランティア活動時間帯の明確化と周知徹底
読み聞かせ活動の実施時間を明確化し、効果的な周知方法を確立することで、利用者間のトラブルが大幅に減少しています。具体的な取り組みとして以下が挙げられます:
・活動カレンダーのオンライン公開
・館内デジタルサイネージでの活動時間表示
・SNSを活用したリアルタイム情報発信
・予約システムとの連携による混雑予測
・活動場所の事前予約制度の確立
これらの施策により、一般利用者が活動時間を避けて来館するなど、効率的な利用が可能になりました。実際に、活動時間の明確化後は、利用者間のトラブルが約70%減少したという報告もあります。
また、ボランティア側も活動時間を意識するようになり、時間超過や予定外の活動が減少。さらに、活動場所の事前予約制により、場所の取り合いなども解消されています。
本の予約システム活用による貸出機会の平等化について
新しい予約システムの導入により、図書館資料の利用機会の平等化が進んでいます。システムの主な特徴は以下の通りです:
・団体利用の予約上限設定機能
・予約待ち状況の可視化システム
・電子書籍との連携による代替提案
・返却予定日のリマインド機能
・長期予約の自動キャンセル機能
これらの機能により、特定の利用者による本の独占が防止され、より多くの人が公平に資料を利用できるようになっています。実際に、人気絵本の予約待ち時間は平均で40%短縮されました。
また、予約状況の可視化により、利用者が適切な時期に予約を入れることが可能に。特に、季節の絵本や行事関連本の予約が分散され、待ち時間の大幅な短縮につながっています。
さらに、電子書籍との連携により、紙の本が借りられない場合の代替手段も確保。これにより、読書機会の損失も最小限に抑えられています。システム導入後の利用者調査では、90%以上が「以前より本を借りやすくなった」と回答しています。
