マンション暮らしで悩まされる上階の足音問題。特に子どもの走り回りや飛び跳ねは深刻な騒音源になります。日々のストレスは健康被害にもつながりかねません。しかし、適切な対策を講じれば解決の糸口が見えてきます。
ここでは、上階の足音トラブルに悩む方々へ、効果的な対処法や解決策をご紹介します。管理会社への相談や住人間のコミュニケーション、法的対応、防音対策など、様々な角度から問題解決の方法を解説します。
騒音問題の現状と影響

上階からの足音問題は、多くのマンション居住者が直面する悩みです。特に子どもの活発な動きは、下の階に響きやすい構造になっています。こうした騒音は単なる不快感にとどまらず、ストレスや睡眠障害などの健康問題を引き起こす可能性があります。日常生活の質を大きく左右する騒音問題。その実態と影響について、詳しく見ていきましょう。
マンションでよくある上階の足音トラブル
マンションにおける上階からの足音トラブルは、建物の構造上避けられない側面があります。特に築年数が経った物件や、薄い床材を使用している場合に顕著です。一般的な足音だけでなく、家具の移動音や落下音なども問題になります。
具体的な騒音の種類:
- 歩行音(特にヒールの音)
- 子どもの走り回る音
- 椅子の引きずり音
- 掃除機の使用音
この音は下の階に住む人々にとって大きなストレス源となります。特に夜間や早朝の騒音は、睡眠を妨げる要因になるでしょう。日中であっても、在宅勤務や休息時間の妨げになる場合があります。
騒音の程度は建物によって異なりますが、防音性能の低い物件では日常的な動きでさえ大きな音になることがあります。このような環境では、上下階の住人間でトラブルが発生しやすくなります。
子どもの走り回りや飛び跳ねによる騒音被害
子どもの元気な動きは、特に深刻な騒音問題を引き起こします。その理由は、子どもの動きが予測不可能で、衝撃が大きいためです。走り回りや飛び跳ねは、床を通じて下の階に直接振動を伝えます。
子どもの騒音で起こりがちな問題:
- 突発的な大きな音による驚き
- 継続的な音による集中力の低下
- 夜間の騒音による睡眠妨害
親にとっては通常の子どもの行動でも、下の階の住人にとっては耐え難い騒音になることがあります。特に乳幼児のいる家庭では、夜泣きなども加わり、状況はより複雑になり、子育て世帯と周囲の住人との間に軋轢を生む原因になってきます。
騒音ストレスが引き起こす健康被害と生活への影響
長期間にわたる騒音ストレスは、身体的・精神的な健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。慢性的な騒音にさらされることで、様々な健康問題が引き起こされる危険性があるのです。
騒音による主な健康被害:
- 睡眠障害
- 高血圧
- 集中力低下
- 不安やイライラの増加
睡眠の質が低下すると、日中の生活にも支障をきたします。仕事や学業のパフォーマンスが落ちる他、人間関係にも悪影響を与えかねません。
- 慢性的な疲労感
- 免疫力の低下
- うつ症状の発現
これらの症状は、単に不快というレベルを超えて、生活の質を著しく低下させる要因になります。特に在宅勤務が増えた現代では、自宅での騒音問題はより深刻になっています。
騒音ストレスへの対処は、単に我慢するだけでは解決しません。適切な対策を講じ、快適な生活環境を取り戻すことが重要です。次のセクションでは、具体的な対策方法について詳しく見ていきましょう。
上階の足音対策と解決方法
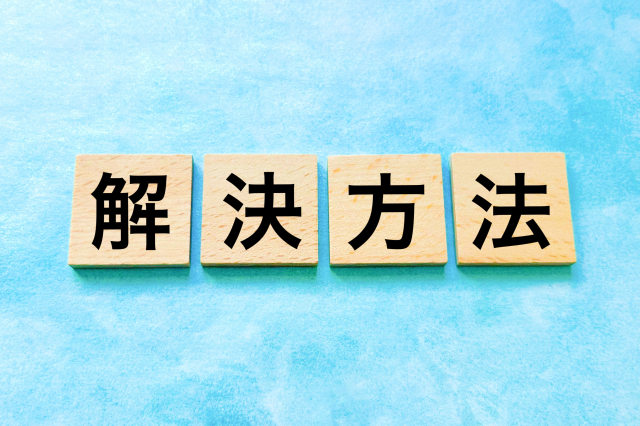
上階からの足音問題に対しては、段階的なアプローチが効果的です。まずは管理会社や管理人に相談し、状況を伝えることから始めましょう。同時に、上階の住人とのコミュニケーションも重要になります。問題解決のためには、騒音の実態を客観的に把握することも必要です。ここでは、これらの対策方法について詳しく解説していきます。
管理会社や管理人への相談と対応依頼のタイミング
管理会社や管理人への相談は、騒音問題解決の第一歩となります。彼らは建物の構造や過去のトラブル事例に詳しく、適切なアドバイスを提供してくれる可能性があります。
相談のタイミングとしては、騒音が日常生活に支障をきたし始めたら早めに行動することをおすすめします。具体的には、以下のような状況が当てはまる場合です:
- 睡眠が妨げられる
- 仕事や勉強に集中できない
- 精神的ストレスを感じる
管理会社への相談時には、問題の具体的な内容を明確に伝えることが重要です。騒音の種類、頻度、時間帯などを詳しく説明しましょう。できれば、騒音の記録や測定結果があれば、より説得力が増します。
管理会社の対応としては、以下のようなものが考えられます:
- 上階の住人への注意喚起
- 建物の構造確認
- 専門業者による調査の手配
場合によっては、管理規約の見直しや、建物全体の防音工事の検討につながることもあります。ただし、即座の解決は難しいケースも多いので、根気強く交渉を続けることが大切です。
管理会社との交渉が行き詰まった場合は、区分所有者会や理事会への相談も選択肢の一つです。集合住宅全体の問題として取り上げてもらうことで、より効果的な対策が講じられる可能性があります。
上階の住人とのコミュニケーション方法と注意点
上階の住人との直接的なコミュニケーションは、騒音問題解決の鍵となる場合があります。しかし、適切なアプローチを取らないと、かえって関係を悪化させてしまう危険性もあります。以下、効果的なコミュニケーション方法と注意点をご紹介します。
コミュニケーションの取り方:
1.まずは丁寧な挨拶から始める
2.問題を具体的に、冷静に説明する
3.相手の立場も考慮しつつ、協力を求める
4.一緒に解決策を考える姿勢を示す
注意点としては、感情的にならないことが重要です。相手を責めるような言い方は避け、事実に基づいた説明を心がけましょう。
効果的な伝え方の例:
「お子さまの元気な様子が聞こえてきます。私も子育ての大変さは理解していますが、夜間は少し静かにしていただけると助かります。」
避けるべき伝え方:
「いつも子どもの騒音がうるさくて迷惑しています。きちんとしつけてください。」
場合によっては、直接対面でのコミュニケーションが難しいこともあるでしょう。そういった際は、管理会社を通じて匿名で伝えてもらう方法もあります。
コミュニケーションを取る際の準備として、以下の点も考慮しましょう:
- 騒音が特に気になる時間帯を把握しておく
- 具体的な解決案を考えておく(例:夜9時以降は走り回らないなど)
- 自分にできる協力点も提案する(例:防音マットの共同購入など)
上階の住人との良好な関係を築くことができれば、日常的な配慮にもつながり、長期的な解決に結びつく可能性が高まります。しかし、相手が非協力的な場合は、無理にコミュニケーションを取ろうとせず、管理会社や専門家に相談することを検討しましょう。
騒音記録と証拠収集の重要性
騒音問題の解決には、客観的な証拠が重要な役割を果たします。感覚的な訴えだけでなく、具体的なデータがあることで、問題の深刻さを相手に理解してもらいやすくなります。また、法的措置を取る際にも、これらの記録が重要な証拠となります。
騒音の記録方法:
- 日時と騒音の種類を詳細に記録する
- 騒音の継続時間を記載する
- 騒音によって受けた影響(睡眠妨害など)も記録する
これらの記録は、騒音日誌としてまとめておくと良いでしょう。スマートフォンのメモアプリや、専用の騒音記録アプリを活用するのも効果的です。
証拠収集の際の注意点:
- プライバシーを侵害しない範囲で行う
- 録音や録画を行う場合は法的な制限に注意する
- 長期間にわたる記録を心がける
騒音の客観的な測定も重要です。騒音計を使用したり、スマートフォンアプリで簡易的に測定したりすることで、数値化された証拠を得ることができます。次の項目では、これらの測定方法についてより詳しく解説します。
騒音計を使った数値化と自治体の貸し出しサービス
騒音問題の客観的な評価には、専門的な騒音計を使用するのが最も正確です。騒音計は、音の大きさをデシベル(dB)単位で測定し、数値化することができます。これにより、騒音の程度を明確に示すことが可能になります。
多くの自治体では、住民向けに騒音計の貸し出しサービスを行っています。このサービスを利用することで、専門的な機器を使った正確な測定が可能になります。
自治体の騒音計貸し出しサービスの利用方法:
1.居住地の自治体の環境課や生活環境課に問い合わせる
2.貸し出し可能な日程を確認し、予約を入れる
3.使用方法の説明を受け、必要書類に記入する
4.指定された期間内に測定を行い、返却する
測定の際の注意点:
- 測定する時間帯や場所を適切に選ぶ
- 複数回測定を行い、平均値を算出する
- 測定結果をきちんと記録し、日時や条件も併せてメモする
- 窓の開閉状態
- 天候
- 周囲の環境音の有無
騒音計を使用した測定結果は、問題解決に向けた交渉や相談の際に有力な証拠となります。自治体の基準値と比較することで、騒音の程度が客観的に評価できます。
ただし、騒音計の操作には一定の知識が必要です。使用方法を十分に理解し、適切に測定することが重要です。分からない点があれば、貸し出し時に自治体の担当者に詳しく聞いておくとよいでしょう。
スマートフォンアプリを活用した簡易的な騒音測定方法
専門的な騒音計を入手できない場合や、日常的に手軽に騒音を測定したい場合、スマートフォンアプリを活用する方法があります。多くのアプリが無料または低価格で提供されており、簡単に騒音レベルを測定できます。
人気の騒音測定アプリの機能:
- デシベル値の表示
- 時間経過によるグラフ化
- 測定結果の保存や共有
アプリを使用する際の注意点:
1.スマートフォンの機種によって精度が異なる
2.専門機器ほどの正確さはない
3.環境音の影響を受けやすい
測定の信頼性を高めるためには、複数回の測定を行い、平均値を算出することをおすすめします。測定時は、スマートフォンのマイク部分を騒音源に向け、安定した場所に設置しましょう。
- 壁際や窓際での測定
- 静かな環境での測定
- 定期的な測定の実施
アプリで得られたデータは、日々の騒音レベルの変化を把握するのに役立ちます。長期的な記録を取ることで、騒音問題の傾向や深刻度を示す資料となります。
ただし、法的な手続きや公式な申し立ての際には、専門機器による測定結果が求められる場合が多いです。スマートフォンアプリは、あくまで個人的な参考データとして活用するのが適切でしょう。
日常的な騒音チェックと、専門機器による正確な測定を組み合わせることで、より効果的な騒音対策が可能になります。
法的対応と専門家への相談

騒音問題が深刻化し、当事者間での解決が困難な場合、法的対応を検討する段階に入ります。この過程では、専門家のアドバイスが非常に重要になります。無料法律相談の活用や、弁護士への相談を通じて、適切な対応方法を見出すことができます。
法的対応には様々な選択肢がありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります。調停や訴訟など、状況に応じた適切な手段を選ぶ必要があります。
無料法律相談の活用と弁護士への相談のタイミング
騒音問題で法的アドバイスが必要になった場合、まずは無料法律相談を利用するのがよいでしょう。多くの自治体や弁護士会が提供しているこのサービスでは、経験豊富な弁護士から初期段階のアドバイスを受けられます。
無料法律相談の利用方法:
1.地域の弁護士会や法テラスに問い合わせる
2.相談日時を予約する
3.問題の概要と証拠資料を準備する
4.相談時間内で的確に状況を説明する
無料相談では時間が限られているため、事前に相談内容を整理しておくことが大切です。騒音の記録や測定結果など、客観的な資料を用意しておくとよいでしょう。
弁護士への正式な相談を検討するタイミング:
- 管理会社や当事者との交渉が行き詰まった場合
- 騒音被害が長期化し、健康被害が出始めた場合
- 賠償請求や強制退去など、法的手続きを検討する段階
弁護士に相談する際は、以下の点に注意しましょう:
- 専門分野(不動産・近隣トラブル)を確認する
- 費用体系を事前に確認する
- 複数の弁護士に相談し、比較検討する
弁護士への相談は、問題解決への大きな一歩となります。専門的な知識と経験を持つ弁護士のアドバイスは、今後の対応方針を決める上で非常に有益です。
法的対応は時間と費用がかかる場合が多いので、慎重に検討する必要があります。弁護士との相談を通じて、自分の状況に最適な解決方法を見出していくことが大切です。
調停や訴訟など法的手段の選択肢と注意点
騒音問題の解決に向けた法的手段には、いくつかの選択肢があります。状況に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。
主な法的手段:
1.調停
2.訴訟(民事裁判)
3.行政による指導・勧告の要請
調停は裁判所が仲介役となり、当事者間の話し合いによる解決を目指す方法です。比較的費用が抑えられ、関係悪化を最小限に抑えられる利点があります。
訴訟は、最終的な解決手段として位置付けられます。裁判所の判断に基づいて問題を解決しますが、時間と費用がかかり、関係修復が困難になる可能性もあります。
行政による指導・勧告は、騒音規制法などに基づいて行われます。法的拘束力は弱いものの、公的機関からの指導という点で効果が期待できます。
各手段の特徴:
調停:
- 柔軟な解決が可能
- 非公開で行われる
- 合意形成が難しい場合もある
訴訟:
- 法的拘束力のある解決が得られる
- 時間と費用がかかる
- 関係修復が困難になる可能性がある
行政指導:
- 比較的迅速に対応が得られる
- 費用負担が少ない
- 強制力に欠ける面がある
法的手段を選択する際の注意点:
- 問題の深刻度と緊急性を考慮する
- 証拠の十分性を確認する
- 費用対効果を検討する
- 長期的な影響を考える
- 近隣関係への影響
- 精神的・時間的負担
- 解決後の生活環境
どの方法を選択するにせよ、専門家のアドバイスを受けながら慎重に判断することが大切です。法的手段に訴える前に、当事者間での話し合いや専門家による仲介など、他の解決方法も十分に検討しましょう。
騒音対策グッズと防音リフォーム

上階からの足音問題に対して、物理的な対策を講じることも有効な解決方法の一つです。防音マットや遮音シートなどの対策グッズを活用したり、天井や床への防音工事を行ったりすることで、騒音を軽減できる場合があります。
ここでは、効果的な防音対策グッズの選び方や使い方、防音工事の種類や費用相場について詳しく解説します。賃貸物件でも実施可能な簡易的な防音対策テクニックもご紹介しますので、自身の状況に合わせた対策を検討してみてください。
効果的な防音マットや遮音シートの選び方と使い方
防音マットや遮音シートは、比較的手軽に導入できる騒音対策グッズです。適切な製品を選び、正しく使用することで、ある程度の効果が期待できます。
防音マットの選び方:
- 厚みと密度を確認する(厚いほど効果が高い)
- 素材を吟味する(ウレタン、EVA樹脂、コルクなど)
- サイズと形状が部屋に適しているか確認する
遮音シートの選び方:
- 遮音性能(音響透過損失)を確認する
- 重量と厚さのバランスを考慮する
- 施工のしやすさを検討する
使用する際のポイント:
1.床全体をカバーするように敷き詰める
2.隙間なく設置する
3.家具の下にも敷く
騒音の種類によって効果的な対策が異なることに注意しましょう。高周波の音には吸音材が、低周波の音には制振材が効果的です。
防音マットや遮音シートの使用上の注意点:
- 湿気がこもらないよう、定期的に掃除や換気を行う
- 重量物の下に敷く場合は、へたりに注意する
- 賃貸物件の場合は、原状回復が必要になることがある
- 床材を傷つけないよう注意する
- 接着剤の使用は慎重に検討する
- 防火性能にも配慮する
対策グッズは、完全な騒音遮断は難しいものの、ある程度の軽減効果が期待できます。特に、軽度から中程度の騒音問題に対しては有効な解決策となるでしょう。
より高度な防音効果を求める場合は、専門業者による防音工事を検討する必要があります。次の項目では、天井や床への防音工事について詳しく解説します。
天井や床への防音工事の種類と費用相場
より本格的な騒音対策として、天井や床への防音工事があります。これらの工事は、専門業者によって行われ、高い効果が期待できます。
主な防音工事の種類:
1.天井吊り下げ工事
2.床上げ工事
3.防音壁工事
天井吊り下げ工事は、既存の天井に新たな天井を設置する方法です。空気層を作ることで、上階からの音を効果的に遮断します。
床上げ工事は、床に防音材を敷き詰め、その上に新しい床材を施工する方法です。歩行音や落下音の軽減に効果があります。
防音壁工事は、壁の内部に防音材を充填したり、壁を二重にしたりする方法です。隣室からの音漏れを防ぐのに効果的です。
工事の費用相場:
- 天井吊り下げ工事:1畳あたり2~5万円
- 床上げ工事:1畳あたり3~6万円
- 防音壁工事:1㎡あたり1~3万円
実際の費用は、部屋の広さや工事の内容、使用する材料によって大きく変動します。複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
防音工事を検討する際の注意点:
- 建物の構造上、工事が可能かどうか確認する
- マンションの場合、管理組合の承認が必要な場合がある
- 工事後のメンテナンス方法を確認する
- 工事期間中の生活への影響を考慮する
- 工事による騒音や振動にも配慮が必要
- 防音効果と見た目のバランスを検討する
防音工事は高額になる傾向がありますが、長期的な視点で見ると、生活の質を大きく向上させる投資となる場合があります。特に、持ち家の場合は資産価値の向上にもつながる可能性があります。
ただし賃貸物件の場合は、大規模な工事が難しいケースがほとんどです。次の項目では、賃貸物件でも実施可能な簡易的な防音対策テクニックをご紹介します。
賃貸物件でもできる簡易的な防音対策テクニック
賃貸物件では大規模な工事が難しいことが多いですが、簡単に実施できる防音対策テクニックがあります。これらの方法を組み合わせることで、ある程度の騒音軽減効果が期待できます。
家具の配置による対策:
- 本棚や大型家具を騒音源側の壁に寄せて配置する
- クローゼットや収納家具を音の通り道に設置する
- ソファやベッドを壁から少し離して置く
この方法は家具が音の緩衝材として機能することで効果を発揮します。特に、本や衣類などが詰まった家具は吸音効果が高くなります。
壁面や窓の対策:
1.厚手のカーテンを使用する
2.防音カーテンを導入する
3.窓に吸音パネルを設置する
厚手のカーテンや専用の防音カーテンは、外部からの騒音だけでなく、室内の反響音も軽減する効果があります。窓に取り付ける吸音パネルは、賃貸物件でも比較的導入しやすい対策です。
床面の対策:
- 厚手のラグやカーペットを敷く
- コルクマットやウッドカーペットを使用する
- 防音スリッパを活用する
上階への音漏れを軽減するだけでなく、室内の足音や反響音も和らげる効果があります。特に、コルクマットは衝撃吸収性が高く、足音の軽減に効果的です。
簡易的な壁面補強:
- 防音シートを壁に貼る
- 布製のタペストリーを掛ける
- 吸音パネルを設置する
これらの方法は、壁面の音の反射を抑え、室内の音環境を改善します。防音シートは粘着タイプのものを選ぶと、賃貸物件でも手軽に導入できます。
ドアの隙間対策:
- ドア下部にすき間テープを貼る
- ドアストッパーを使用する
- 防音ドアシートを取り付ける
ドアの隙間は意外と音が漏れやすい箇所です。これらの対策で、廊下側からの音の侵入を軽減できます。
- 換気口や通気口のカバー使用
- コンセントボックスの隙間塞ぎ
- 家電製品の下に防振マットを敷く
これらの小さな対策の積み重ねが、全体的な防音効果を高めます。一つ一つは小さな効果でも、組み合わせることで相乗効果が期待できます。
注意点として、過度な防音対策は室内の換気を妨げる可能性があります。定期的な換気を心がけ、湿気対策にも気を配りましょう。
賃貸物件での防音対策は、原状回復が必要になる点に留意が必要です。退去時に簡単に元の状態に戻せる方法を選ぶのがよいでしょう。
これらの簡易的な対策で十分な効果が得られない場合は、家主や管理会社と相談し、より本格的な防音対策の可能性を探ることも検討してみてください。
引っ越しを検討する場合の注意点

上階からの騒音問題が解決困難な状況に陥った場合、最終的な選択肢として引っ越しを検討することがあります。新しい住居を選ぶ際には、騒音トラブルを避けるためのポイントを押さえることが重要です。
ここでは、物件選びの際に注意すべき点や、騒音リスクの低い住居オプションについて詳しく解説します。快適な住環境を手に入れるための指針として参考にしてください。
騒音トラブルを避けるための物件選びのポイント
新居を探す際、騒音問題を事前に回避するためのチェックポイントがいくつかあります。これらを意識して物件を選ぶことで、将来的な騒音トラブルのリスクを軽減できます。
建物の構造と築年数:
- 鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)を選ぶ
- 新築や比較的築年数の浅い物件を検討する
- 二重床や二重天井構造の物件を探す
RC造やSRC造は、木造や軽量鉄骨造に比べて遮音性能が高い傾向にあります。築年数が浅い物件は、最新の遮音技術が採用されている可能性が高くなります。
部屋の位置:
1.角部屋を選ぶ
2.上階がない最上階の物件を検討する
3.エレベーターや階段から離れた部屋を選ぶ
角部屋は隣接する部屋が少ないため、騒音の影響を受けにくいです。最上階は上階からの騒音がなく、エレベーターや階段から離れた部屋は人の往来による騒音が少なくなります。
周辺環境:
- 主要道路や線路から離れた場所を選ぶ
- 商業施設や繁華街から一定の距離がある地域を探す
- 静かな住宅街や緑の多い環境を優先する
外部からの騒音も生活の質に大きく影響します。周辺環境をしっかりチェックし、静かな環境を選びましょう。
物件内の確認ポイント:
- 内覧時に上階や隣室の音をよく聞く
- 壁や床を軽く叩いて音の伝わり方を確認する
- 窓の遮音性能を確認する
- 換気扇や給湯器の音をチェック
- ドアの開閉音を確認
- 配管からの水音に注意を払う
実際に物件を訪れ、様々な角度から音環境をチェックすることが重要です。可能であれば、異なる時間帯に複数回訪問するのも効果的です。
管理体制の確認:
- 管理規約で騒音に関する規定を確認する
- 管理人の常駐有無や対応時間を把握する
- 過去の騒音トラブルの有無や対応状況を聞く
しっかりした管理体制がある物件は、騒音トラブルが発生した際の対応も迅速である可能性が高くなります。総合的に判断し、自分のライフスタイルに合った物件を選ぶことが大切です。
最上階や戸建てなど騒音リスクの低い住居オプション
騒音問題を根本的に回避するためには、構造的に騒音リスクの低い住居オプションを選ぶことが効果的です。ここでは、そうした住居の特徴と選択時の注意点について詳しく見ていきます。
最上階の物件:
- 上階からの足音や振動がない
- 日当たりが良く、眺望が開けている場合が多い
- 屋上からの雨漏りリスクに注意が必要
最上階は上からの騒音がないため、静かな環境が期待できます。ただし、夏場の暑さや冬場の寒さ対策が必要になる場合があります。
メゾネットタイプの物件:
1.上下階が自分の住居スペース
2.階段の音が気にならない
3.開放感のある空間を楽しめる
メゾネットタイプは、上下階の騒音問題を気にせずに生活できる利点があります。ただし、内階段の昇り降りが必要なため、高齢者や小さな子どもがいる家庭では注意が必要です。
一戸建て住宅:
- 隣家との距離が取れる
- 自由度の高いリフォームが可能
- メンテナンス費用に注意が必要
一戸建ては隣家との距離が確保できるため、騒音問題のリスクが低くなります。ただし、外部からの騒音(道路や商業施設など)には注意が必要です。
低層マンション:
- エレベーターの音や振動が少ない
- 階段の上り下りが比較的楽
- 高層マンションに比べて住民同士の距離感が近い
低層マンションは、高層マンションに比べて全体的に静かな環境が期待できます。ただし、1階の場合は通行人の音や虫の侵入などに注意が必要です。
防音設計された物件:
- 二重床や二重天井構造
- 高性能な遮音材使用
- 防音サッシ採用
最新の防音技術を採用した物件は、騒音問題のリスクが大幅に低減されます。ただし、一般的に賃料や価格が高めになる傾向があります。
- テラスハウスやタウンハウス
- コーポラティブハウス
- サービス付き高齢者向け住宅
それぞれの特性によって騒音リスクが低くなる可能性があります。
選択時の注意点:
- 予算との兼ね合いを十分に考慮する
- 通勤や生活利便性とのバランスを取る
- 将来的なニーズの変化も想定する
騒音リスクの低い住居オプションは、一般的に価格帯が高くなる傾向があります。長期的な視点で、生活の質と費用対効果を慎重に検討することが大切です。
最終的には、自分のライフスタイルや優先順位に合わせて、最適な選択をすることが重要です。騒音問題だけでなく、総合的な住環境の良さを判断基準にしましょう。
