昨今の大学受験において「塾なしでは合格できない」という認識が広がっています。しかし実際には進学校に通う生徒の中には塾に頼らず自力で難関大学に合格する事例が少なからず存在します。特に高校の指導体制がしっかりしている地域や学校では、塾に通わずとも十分な受験対策が可能です。
地方と都市部では塾の必要性に対する認識に差があり、地方ではむしろ学校の授業と自主学習だけで難関国立大に合格する生徒が珍しくありません。自己管理能力と学習計画の立て方が確立されていれば、塾に通う時間を自宅学習に充てることでより効率的に学力を伸ばす選択肢も有効です。
大学受験における塾の役割は「勉強を教える場」から「情報収集と効率的な対策」へと変化しています。必要性は志望大学や高校のタイプ、本人の学習スタイルによって大きく異なるため、一概に「必須」とは言い切れません。本記事では塾なし大学受験の実態と成功のための具体的なポイントを解説します。
塾なし大学受験の現状と実際の体験談

現代の大学受験において塾なし合格は珍しいと思われがちですが、実際には進学校生の中で一定数の「塾なし合格者」が存在します。特に地方の進学校では塾に行かずとも高校の授業と自主学習だけで旧帝大を含む難関国立大学に合格する生徒が少なくありません。
地域差は顕著で、都市部では中学受験から塾文化が根付いている一方、地方では学校の補習や自習が充実していることがあります。「高校が塾の役割を果たしている」という声もあり、地域の教育環境によって塾の必要性は大きく変わってきます。
近年ではオンライン学習ツールやYouTube授業など、独学でも質の高い学習が可能になったことから、自分に合った学習スタイルを確立できれば塾なしでも十分に戦えるという現実があります。重要なのは画一的な「塾ありき」の考えではなく、個々の状況に応じた最適な受験戦略を立てることです。
今も塾なしで難関国立大学に合格している学生たち
「塾なしで大学受験」と聞くと時代遅れに感じる人もいるかもしれませんが、現在でも難関国立大学に塾なしで合格する学生は確実に存在します。ある進学校では毎年数名の生徒が塾に通わずに旧帝大に合格しています。彼らに共通するのは「自分で計画を立てて実行する力」と「高校の授業を最大限活用する姿勢」です。
塾なし合格者の特徴として挙げられるのが、高い自己管理能力と効率的な学習方法の確立です。彼らの多くは「塾に通う時間がもったいない」という考えを持ち、その時間を自習に充てています。高校の授業を真剣に受け、わからない点は教科担当に質問する習慣をつけることで、追加の指導なしでも高いレベルの学習が可能になります。
地方の進学校ではトップ層の生徒が「学校の指導だけで十分」と考えるケースが多く見られます。実際に県トップクラスの公立高校では、授業と定期的な課題、模試対策が充実しており、塾に行く必要性を感じない生徒が珍しくありません。学校によっては0限・7限授業や長期休暇中の補習など、実質的に塾と同等以上の機能を果たしている事例もあります。
特に理系科目に強い生徒は独学でも伸びる傾向があり、参考書と問題集を計画的にこなすことで十分な実力を養うことが可能です。国公立大学志望者の場合、共通テスト対策は学校の授業でカバーされることが多く、二次試験対策も赤本などを活用して自力で対応できる生徒が一定数います。
学校の先生からの個別指導やアドバイスを積極的に求めることで、塾講師に頼らずとも専門的な指導を受けられることも塾なし合格の大きな要因です。教員の中には難関大学の出身者も多く、適切な質問をすることで貴重な受験情報を得ることができます。
地方と都市部での塾なし受験事情の違い
地方と都市部では大学受験における塾の位置づけが大きく異なります。都市部では小学生から塾通いが当たり前という環境があるのに対し、地方では進学校に通う生徒の中でも塾に行かない選択をする生徒が珍しくありません。この背景には教育環境の違いがあります。
地方の進学校では学校自体が受験指導に力を入れていることが多く見られます。補習授業や長期休暇中の講習が充実しており、実質的に塾の役割を学校が担っているケースがあります。県内トップ校などでは定期的な模試や課題添削など、手厚い進学指導体制が整っていることで、あえて塾に通う必要性を感じない生徒が一定数存在します。
一方、都市部では受験競争が激しく、情報戦の様相を呈していることから塾通いが一般的です。特に私立大学受験においては、各大学の出題傾向や対策方法など、専門的な情報を得るために塾を活用する生徒が大半を占めています。都市部の公立高校では「大学の予備校ではない」という方針から受験指導に消極的な学校もあり、必然的に塾に頼らざるを得ない状況が生まれています。
地方では大学受験においても国公立一本に絞る傾向があるのに対し、都市部では私立大学を含めた複数校受験が一般的です。国公立大学は試験科目や出題範囲が明確で学校の授業内容との関連性が高いため独学でも対応しやすい反面、私立大学は独自の入試形式や出題傾向があり、対策には専門的な知識が必要になることが多いです。
通学距離の問題も見逃せません。地方では塾までの距離が遠いケースが多く、移動時間を考えると効率的でないと判断する家庭も少なくありません。オンライン学習が普及した現在では、地方在住でも質の高い学習コンテンツにアクセスできるようになり、この点での不利は解消されつつあります。
地域による教育格差は依然として存在しますが、インターネットの普及により情報格差は縮小傾向にあります。地方でも都市部と同等の受験情報を入手できる環境が整いつつあり、塾なし受験の可能性はむしろ広がっているとも言えるでしょう。
昭和と令和の大学受験環境の変化
昭和時代の大学受験と現代の受験環境には大きな違いがあります。共通一次試験時代(昭和50年代)には地方でも予備校や塾は少なく、高校の指導と自主学習で難関大学に合格するケースが一般的でした。当時は受験システムも単純明快で、国立大学なら同じ科目を全員が受験するという形式だったため、対策も立てやすい環境でした。
令和になった現在、大学入学共通テストの導入や入試の多様化により、受験システムは複雑化しています。入試科目の選択肢が増え、総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜など、従来の学力試験以外の入試形態も重要性を増しています。このような変化により、受験情報を収集・分析する能力がより重要になり、塾や予備校の「情報提供機能」が注目されるようになりました。
学習内容自体も難化している面があります。英語一つとっても、共通一次時代と比較して語彙数や読解速度は大幅に増加しています。現代の共通テストでは80分で6000語以上の英文を処理する能力が求められ、これは昭和時代の試験の約3倍のスピードに相当します。こうした難化に対応するため、専門的な対策を提供する塾の需要が高まっています。
受験生の数と大学進学率の変化も見逃せません。18歳人口は減少している一方で大学進学率は上昇し続けており、現在は高校卒業者の約50%が大学に進学します。選択肢が増えたことで「受験情報戦」の様相を呈しており、特に都市部では効率的な受験戦略を立てるために塾を活用するケースが増えています。
学習ツールの多様化も大きな変化です。インターネットの普及により、YouTube講義や無料の学習サイト、オンライン予備校など、自宅で質の高い学習コンテンツにアクセスできるようになりました。これにより従来の「通塾型」ではない新しい学習スタイルが確立されつつあり、必ずしも物理的な塾に通わなくても効果的な受験対策が可能になっています。
社会全体の価値観の変化として、「効率性」や「確実性」を重視する傾向が強まっていることも塾利用の増加に影響しています。かつての「独学の努力」を美徳とする考え方から、「効率的に結果を出す」ことを重視する考え方へのシフトが見られ、費用対効果の観点から塾を利用する家庭が増えています。
塾なし受験を成功させる要素と条件
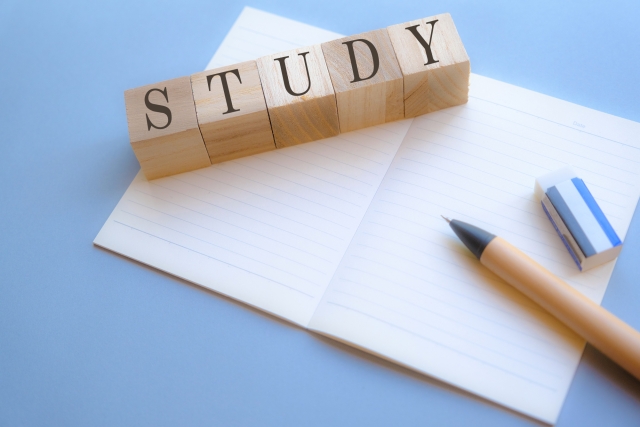
塾なしで大学受験に成功するためには、いくつかの重要な要素と条件が存在します。何より高校の授業を最大限に活用する姿勢が不可欠で、授業中の集中力や質問する積極性が成否を分けることになります。
高校によっては補習授業や定期的な模擬試験、進路指導が充実しており、こうした環境を活かすことができる生徒は塾に通う必要性が低くなります。特に地方の進学校では放課後の補習や長期休暇中の講習が手厚く、実質的に塾の役割を学校が担っているケースが見られます。
自己管理能力と計画性も塾なし受験の鍵となります。自分で学習計画を立て、それを着実に実行できる生徒は塾の管理がなくても高い学力を獲得できます。このような自律性は大学入学後や社会人になってからも役立つスキルであり、塾なし受験の副産物とも言えるでしょう。
高校の進学指導体制と補習授業の重要性
高校の進学指導体制は塾なし受験の成否を左右する重要な要素です。進学校と呼ばれる高校の中には、放課後の補習や長期休暇中の講習が充実しており、実質的に塾と同等以上の指導が受けられる環境が整っています。このような学校では7時限・8時限授業や土曜授業が実施されており、通常の授業時間以外にも受験対策のための時間が確保されています。
特に地方の進学校では「トップ校」としてのプライドから手厚い進学指導を行うケースが多く、教員が熱心に生徒の質問に応じたり、個別の添削指導を行ったりすることで、塾に頼らずとも高い学力を身につけることが可能です。実際に多くのレスポンスから「高校が塾の役割を果たしていた」という声が聞かれます。
学校が定期的に模擬試験を実施している点も重要です。外部模試を学校で受験する機会が多ければ、わざわざ塾に通って模試を受ける必要性は低くなります。進学校では週末に模試が組み込まれているケースもあり、自分の立ち位置を把握し、弱点を発見する機会が十分に確保されています。
教員の質も見逃せない要素です。難関大学出身の教員が多い高校では、受験のコツや効果的な学習法についての指導が期待できます。特に二次試験対策では、教科に精通した教員からのアドバイスが非常に有効であり、質問する姿勢さえあれば塾講師に劣らない指導を受けることができます。
学校の進路指導部が提供する情報の質と量も重要です。大学の入試情報や過去の合格実績、志望校選定のアドバイスなど、適切な進路指導があれば塾に通う主な理由の一つである「情報収集」の必要性は大幅に減少します。一部の進学校では予備校から講師を招いて進路説明会を開催するなど、外部の専門的知見を取り入れる工夫も見られます。
補習授業の内容と質も塾なし受験の可能性を左右します。単なる授業の繰り返しではなく、発展的な内容や受験対策に特化した補習が行われていれば、塾で学ぶ内容との差は小さくなります。特に共通テスト対策や二次試験対策に焦点を当てた補習は、塾なし受験生にとって貴重な機会となります。
学校の学習環境も重要な要素です。自習室が整備されており、放課後や休日も利用できる環境があれば、集中して勉強するスペースが確保されます。図書館の充実度や参考書・問題集の貸出制度なども、自主学習をサポートする重要な要素となります。
自己管理能力と学習計画の立て方
塾なしで大学受験に挑む場合、最も重要になるのが自己管理能力です。塾では学習計画が立てられ、課題の締め切りが設定されることで強制的に勉強を進めることができますが、塾なしの場合はこれらすべてを自分で管理する必要があります。自分に合った学習計画を立て、それを着実に実行する力が成功の鍵となります。
効果的な学習計画を立てるには、志望校の出題傾向を把握し、それに合わせた教材選びから始める必要があります。赤本(過去問)を分析して、各科目でどのような知識や解法が求められているかを理解し、それに基づいて優先順位をつけることが大切です。時間の使い方についても、各科目にどれくらいの時間を割くべきか、自分の得意・不得意を考慮して配分することが効率的な学習につながります。
計画を立てる際は具体的かつ実行可能なものにすることが重要です。「英語を勉強する」という曖昧な目標ではなく、「英単語を50個覚える」「長文読解を1題解く」といった具体的な行動に落とし込むことで、達成感を得やすく、継続的な学習につながります。日々の予定を手帳やアプリに記録し、終わったタスクにチェックを入れることで進捗を視覚化する工夫も有効です。
自己分析と定期的な見直しも欠かせません。模試の結果や日々の学習で感じた手応えを基に、自分の弱点を把握し、計画を適宜修正していくことが大切です。当初の計画通りに進まないことも多々ありますが、その場合は柔軟に対応し、現実的な計画に調整する柔軟性も必要です。
学習環境の整備も自己管理の重要な要素です。自宅で集中できる環境を作ることが難しい場合は、学校の自習室や図書館を活用するなど、自分に合った学習場所を確保することが望ましいです。スマートフォンなどの誘惑を遠ざけ、集中力を持続させる工夫も効果的です。
モチベーション維持のための工夫も必要です。長期的な目標(志望校合格)だけでなく、短期的な目標(週単位の課題達成など)を設定し、小さな成功体験を積み重ねることがモチベーション維持につながります。時には息抜きの時間を計画に組み込むことで、燃え尽き症候群を防ぐことも大切です。
塾なしで成功した先輩の体験談によれば、「塾に行く時間がもったいない」という考えから、その時間を自習に充てることで効率的に学力を伸ばしたケースが多く見られます。自分のペースで理解を深められること、自分で問題を解決する力が身につくことなど、独学ならではのメリットを活かした学習が成功につながっています。
模試や情報収集を自力で行うコツ
塾なし受験で最も不安になりがちなのが「情報不足」です。塾に通えば自動的に最新の受験情報が得られる一方、独学では自分から積極的に情報を集める必要があります。現代はインターネットの普及により、以前よりも格段に情報収集がしやすくなっています。大学のホームページや受験情報サイト、教育委員会の発表など、公式情報は誰でもアクセス可能です。
模試については学校で受験できる機会を最大限活用することが大切です。多くの進学校では年に数回、外部模試を校内で実施しています。これに加えて、自分で申し込む外部模試も検討するとよいでしょう。大手予備校が実施する全国模試は、自分の全国的な立ち位置を知る貴重な機会となります。模試の申込方法や会場情報は各予備校のホームページで確認できます。
模試の結果を活用する際のポイントは、単に偏差値や順位を気にするだけでなく、弱点分析に重点を置くことです。模試の解説冊子には詳細な解説が掲載されているため、間違えた問題について徹底的に復習することで大きな学力向上につながります。特に多くの受験生が間違える問題は配点が高いケースが多いため、そこを克服することで効率的に得点アップを狙えます。
志望校の過去問(赤本)の入手と分析は必須です。ほとんどの大学の過去問は書店で購入できますが、大学によっては公式サイトで無料公開している場合もあります。過去問を時間を測って解き、採点することで、本番に近い形での実力チェックができます。解答・解説を読むだけでなく、なぜそのような出題がされているのかを考えることで、出題者の意図を理解することができます。
※過去問分析のポイント
- 出題パターンの把握(毎年似た形式の問題が出題されることが多い)
- 配点の高い分野の特定
- 時間配分の検討(どの問題にどれくらい時間をかけるべきか)
- 解法のバリエーションの研究(模範解答以外の解き方も考える)
学校の先生を情報源として活用することも重要です。進学校の教員は受験情報に精通していることが多く、相談することで貴重なアドバイスが得られます。質問は具体的に行うことがコツで、「この大学はどうですか?」のような漠然とした質問より、「○○大学の△△学部の英語では、どのような問題が出やすいですか?」といった具体的な質問の方が有益な回答を得られやすいです。
大学のオープンキャンパスや入試説明会への参加も有効な情報収集方法です。コロナ禍以降、オンラインでの開催も増えており、地方在住でも参加しやすくなっています。これらのイベントでは入試担当者から直接情報を得られるため、出題傾向や求める学生像について貴重な情報を入手できます。
先輩の体験談も貴重な情報源になります。同じ高校から志望大学に合格した先輩がいれば、勉強法や使用した参考書、時間配分などについて具体的なアドバイスをもらえることがあります。学校によっては「合格体験記」などの形で先輩の体験談が残されていることもあるため、進路指導部に問い合わせてみるとよいでしょう。
情報収集において重要なのは、得た情報を整理・分析する習慣です。ノートやデジタルツールを活用して、入手した情報を志望校ごと、科目ごとに整理しておくことで、必要な時にすぐに参照できるようになります。情報の出所や日付も記録しておくと、情報の新しさや信頼性を判断する際に役立ちます。
塾を利用する本当の価値と意義

塾を利用する価値は単なる「勉強を教えてもらう場所」という認識を超えています。現代の塾や予備校は受験に関する専門的な情報提供機関としての役割が大きく、入試形式の多様化や複雑化に伴い、その価値はむしろ高まっている側面があります。
特に私立大学受験においては各大学の出題傾向や対策法が異なるため、専門家の知見が役立つケースが多いです。塾講師は多数の受験生を指導した経験から、効率的な学習方法や時間配分のアドバイスを提供できます。
塾のもう一つの重要な機能は受験生のメンタル面でのサポートです。受験期は精神的プレッシャーも大きく、モチベーション維持が課題になりがちです。塾では同じ目標を持つ仲間との切磋琢磨や講師からの励ましが受けられ、孤独感を軽減できる環境があります。
塾の価値は個々の状況によって異なり、高校の指導体制や本人の自己管理能力、志望校の特性などを考慮して判断すべきものです。全員に塾が必要というわけではなく、必要な部分だけを上手に活用するという選択肢も検討する価値があります。
受験情報と入試対策における塾の役割
現代の大学受験において塾や予備校が果たす最も重要な役割の一つは、質の高い受験情報の提供です。大学入試は年々複雑化しており、各大学の入試形式や出題傾向、配点基準などは多岐にわたります。塾や予備校はこれらの情報を体系的に収集・分析し、受験生に最適な形で提供する機能を持っています。
特に私立大学受験においては、学校ごとに異なる入試方式や出題傾向があり、独自の対策が必要になることが多いです。塾では各大学の特徴を熟知した講師が、志望校に特化した対策を提供してくれます。早慶上智などの難関私大では、学部や学科によっても出題傾向が異なるため、こうした詳細な情報は塾を通じて得られることが多いです。
受験における「過去問の分析と活用」についても塾は重要な役割を果たします。単に過去問を解くだけでなく、出題者の意図を読み解き、類似問題の発見や効果的な解法のアドバイスなど、専門的な視点からの指導が受けられます。大学によっては「裏技」と呼ばれる効率的な解法や、学校では教えない実践的なテクニックを教えてくれることもあります。
※塾で得られる受験情報の例
- 各大学の出題傾向と対策ポイント
- 併願パターンの設計
- 入試日程の組み立て方
- 推薦入試・総合型選抜の対策
- 面接・小論文対策のノウハウ
進路選択に関するアドバイスも塾の重要な機能です。自分の学力レベルに合った志望校選びや、合格可能性の高い併願パターンの設計など、経験豊富な塾講師のアドバイスは進路決定において大きな助けになります。特に都市部では選択肢が多いため、プロの視点からの進路指導は貴重です。
模擬試験と成績分析も塾の重要な役割です。大手予備校が実施する模試は精度が高く、全国レベルでの自分の立ち位置を正確に把握することができます。模試後の成績分析では、単なる点数や偏差値だけでなく、志望校合格の可能性や弱点分野の特定など、詳細な診断が提供されます。こうした客観的なデータに基づく分析は自己分析の限界を超えるものです。
最新の入試傾向や教育政策の変化に関する情報も塾を通じて得られます。大学入試制度は頻繁に変更されており、こうした変化に敏感に対応することは個人では難しい面があります。塾や予備校は常に最新情報をキャッチし、それに応じた対策を素早く提供できる体制を整えています。
指導経験の蓄積も塾の強みです。多くの受験生を指導してきた経験から、「どのような学習法が効果的か」「どんな躓きが生じやすいか」といったノウハウが蓄積されています。こうした集合知を活用することで、効率的な学習が可能になります。
学校では対応しきれない専門的な質問への回答も塾の重要な機能です。難関大学の問題には高度な応用力を要する問題も多く、そうした問題への対応は専門的な知識を持つ塾講師が得意とする分野です。特に学校の教員が回答に窮するような高度な問題については、塾講師のアドバイスが貴重になります。
受験テクニックと時間効率を高める塾のメリット
塾や予備校の最大のメリットの一つは、効率的な学習方法と受験テクニックを教えてくれることです。大学受験では単に知識を持っているだけでなく、限られた時間内でいかに正確に解答するかが重要になります。特に共通テストのような大量の問題を短時間で処理する必要がある試験では、解法の速さと正確さが合否を分けることもあります。
塾では「問題の読み方」から教えてくれます。設問の意図を素早く把握し、必要な情報だけを効率よく拾い読みする技術や、選択肢の消去法など、学校ではあまり教えない実践的なテクニックを学ぶことができます。英語や国語の長文読解では、全文を読まなくても解答できる方法や、設問から逆算して必要な部分だけを読む技術など、時間効率を高める工夫が教えられます。
数学においては、計算過程を短縮する方法や、パターン化された問題の解法を集中的に学ぶことができます。通常の授業では「なぜそうなるのか」という原理原則を重視しますが、受験対策では「どう解くか」という実践的な解法テクニックも重要です。塾ではこうした効率的な解法を豊富な演習と共に学ぶことができます。
共通テスト対策として、マークシート方式の特性を活かした解答戦略も塾の強みです。選択肢の絞り込み方や、時間配分の最適化、部分点の取り方など、点数を最大化するための戦略的アプローチを学ぶことができます。実際に「いちいち計算をしなくても消去法でマークシートの正解が判る」といった効率的な解法を教えてくれる塾もあります。
志望校別の対策も塾ならではの強みです。同じ科目でも大学によって出題傾向が大きく異なるため、志望校に特化した対策が効果的です。塾では過去の出題傾向を分析し、その大学で頻出するテーマや問題パターンを集中的に学ぶことができます。これにより、限られた時間で最大の効果を得ることが可能になります。
学習計画の立て方と時間管理のコツも塾で学べる重要なスキルです。何をいつまでに、どのレベルまで習得すべきかという具体的なロードマップを示してくれるため、無駄なく効率的に学習を進めることができます。特に複数の科目をバランスよく学習する必要がある受験生にとって、このような計画性は非常に重要です。
弱点の早期発見と的確な補強も塾のメリットです。定期的なテストや小テストを通じて、自分では気づきにくい弱点を客観的に把握し、それを集中的に強化することができます。独学では見過ごしがちな細かな理解不足も、プロの目で発見されることで早期に修正することが可能です。
質問の機会が豊富にあることも大きな利点です。わからない点をその場で質問できる環境は、理解を深め、学習のつまずきを解消する上で非常に効果的です。特に難関大学の入試問題などは、独学では解決が難しい高度な内容も含まれており、専門的な知識を持つ講師のアドバイスが貴重になります。
他の受験生との競争環境も学習効率を高める要因になります。同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨することで、モチベーションが維持され、自然と学習時間が増えることもあります。また、他の優秀な受験生の学習方法を見ることで、自分の勉強法を改善するヒントを得ることもできます。
メンタル面でのサポートとモチベーション維持
大学受験は知識や学力だけでなく、長期間にわたってモチベーションを維持し、精神的なプレッシャーに対処する能力も問われる試練です。この点において塾や予備校は単なる学習指導以上の重要な役割を果たしています。特に受験期特有の不安や焦り、挫折感などの精神的負担を軽減するサポートは、塾の重要な機能の一つと言えるでしょう。
塾では同じ目標に向かって努力する仲間との出会いがあります。孤独な勉強が続くと「自分だけが頑張っている」という錯覚に陥りがちですが、同じ志望校を目指す仲間の存在は大きな心の支えになります。互いに励まし合い、情報交換をすることで、モチベーションの維持につながります。特に家族に受験経験者がいない場合、この仲間との連帯感は非常に重要です。
講師からの精神的サポートも見逃せません。経験豊富な講師は、単に教科内容を教えるだけでなく、受験生の精神状態を理解し、適切な言葉かけやアドバイスを提供してくれます。「この時期はこういう不安が出るのは当然」「ここで挫折感を味わうのは成長の証」といった言葉は、受験生の不安を和らげる効果があります。
定期的な面談や進路相談の機会も、メンタル面でのサポートとして機能します。自分の現状を客観的に把握し、具体的な目標設定や改善点の指摘を受けることで、漠然とした不安が具体的な課題に変わり、対処しやすくなります。特に模試の結果が思わしくなかった時など、精神的に落ち込みやすい時期のフォローは重要です。
目標達成のための道筋を示してくれることも、精神的な安定につながります。「今この位置にいて、こうすれば目標に到達できる」という具体的な見通しがあることで、漠然とした不安が軽減されます。特に受験直前期は焦りや不安が強まりがちですが、明確な戦略があることで冷静さを保ちやすくなります。
小さな成功体験の積み重ねも塾の環境がもたらす利点です。定期的な小テストや課題で成果を実感できる機会があることで、「頑張れば結果が出る」という自信につながります。独学では見落としがちな小さな進歩も、塾の環境では認識されやすく、それが継続的なモチベーション維持に寄与します。
受験本番に向けた心理的準備も塾で学べる重要な要素です。本番と同じ条件での模擬試験や、ミスへの対処法、緊張の和らげ方など、試験当日のパフォーマンスを最大化するためのメンタルトレーニングも、塾では重視されています。こうした準備により、本番での実力発揮が期待できます。
リアルな合格体験談や先輩からのアドバイスに触れる機会も塾ならではのメリットです。「あの人も最初はこんなに苦労したのか」「こうして乗り越えたのか」という具体的なストーリーは、大きな励みになります。特に志望校の合格者の体験談は、目標達成のイメージを具体化するのに役立ちます。
学習の管理と均質化による安心感も重要な要素です。「このカリキュラムをこなせば基礎は固まる」「この講座を終えれば志望校レベルに到達できる」という確信があることで、不安や焦りが軽減されます。特に計画性に不安がある生徒にとって、この「枠組み」が与えられることは大きな安心感につながります。
親や家族のプレッシャーからの解放という側面もあります。家庭では「もっと勉強しなさい」というプレッシャーを感じることも多いですが、塾では専門家が適切な学習量や方向性を示してくれるため、無用なプレッシャーから解放されることもあります。「塾の先生がこう言っている」ということで、家庭内の受験に関する摩擦が軽減されることもあるでしょう。
進学校生の塾なし受験と塾あり受験の選択基準

進学校に通う生徒が塾に通うべきかどうかは、一律に決められるものではありません。この選択には高校の特性、志望大学の傾向、そして何より本人の学習スタイルと自己管理能力が大きく関わってきます。
高校によって授業の質や受験指導の充実度には大きな差があります。進学校と一口に言っても、「大学の予備校ではない」という方針から受験指導に消極的な学校もあれば、7限目まで授業があり土曜日も補習がある徹底した受験指導校もあります。高校の指導がどの程度充実しているかを見極めることが判断の第一歩です。
志望大学によっても塾の必要性は変わります。国公立大学志望の場合は学校の授業内容との関連性が高いため独学でも対応しやすい一方、私立大学は独自の入試形式や出題傾向があり、専門的な対策が必要になることがあります。特に複数の私立大学を受験する場合は、各大学の特性に合わせた対策が必要になるため、塾の情報力が役立つことがあります。
本人の学習スタイルと自己管理能力も重要な判断材料です。自分で計画を立てて着実に実行できる生徒は塾なしでも十分に対応できますが、外部からの管理がないと計画的に勉強が進められない生徒は塾の環境が合っている場合があります。この見極めは本人だけでなく、保護者や教師の客観的な視点も取り入れると良いでしょう。
進学校のタイプ別に見る塾の必要性
進学校と一言で言っても、その特性や指導方針はさまざまです。進学校のタイプによって塾の必要性は大きく異なるため、自分の通う高校の特徴を正確に把握することが重要です。大きく分けると、進学校は「受験指導型」と「自主性重視型」の2つのタイプに分類できます。
受験指導型の進学校では、カリキュラム自体が大学受験を強く意識した内容になっています。7時限・8時限授業や土曜授業が実施されており、長期休暇中も補習や講習が充実しています。このような学校では教員の受験指導も熱心で、過去問分析や志望校対策など、塾と同等以上の指導が受けられることも珍しくありません。地方のトップ校に多いこのタイプの高校では、塾に通わなくても十分な受験対策が可能なケースが多いです。
自主性重視型の進学校は「大学の予備校ではない」という方針を掲げ、基礎学力の定着や探究的な学習に重点を置いています。こうした学校では授業の質は高いものの、具体的な受験テクニックや志望校別の対策などは個人に委ねられることが多いです。都市部の名門校にこのタイプが見られることがあり、この場合は受験対策を補完するために塾を活用するケースが増えます。
中高一貫校の場合も特徴があります。私立の中高一貫校では独自のカリキュラムで効率的に学習を進め、高校3年次には既に大学レベルの内容に踏み込んでいることもあります。内部進学制度が充実している中高一貫校では、系列大学への進学を前提とした指導が行われており、その場合は塾に通う必要性は低くなります。一方で、外部の大学を志望する場合は、学校のカリキュラムと受験対策にギャップがあることもあり、その補完として塾を利用することがあります。
公立トップ校では地域によって特性が異なります。地方のトップ校では国公立大学合格を重視した指導体制が整っていることが多く、教員の面倒見も良い傾向があります。こうした環境では塾なしで難関大学に合格する生徒も珍しくありません。一方、都市部の公立トップ校では競争が激しく、学校の指導だけでは不十分と感じて塾を利用する生徒が多い傾向があります。
学校の設備や環境も重要な要素です。自習室や図書館が充実しており、放課後や休日も利用できる環境があれば、集中して勉強するスペースが確保されます。質問対応の機会が豊富にあるかどうかも重要で、放課後に教員が質問を受け付ける体制が整っている学校では、塾講師に質問する必要性が低くなります。
部活動との両立も考慮すべき点です。部活動に力を入れている進学校では、引退時期が受験に与える影響が大きくなります。3年夏まで本格的な部活動がある場合、引退後の受験対策を効率的に行うために塾を活用するケースがあります。一方、文化部や帰宅部の生徒は時間的余裕があるため、独学で十分と判断することもあります。
校風や学校の雰囲気も塾の必要性に影響します。互いに切磋琢磨する環境がある学校では、自然とモチベーションが維持され、情報交換も活発に行われます。こうした環境では塾に通わなくても高いレベルの学習ができることがあります。逆に受験に対する意識が低い環境では、外部の刺激を求めて塾に通うことも考えられます。
教員の質と面倒見の良さも大きな要素です。難関大学出身の教員が多く、受験のコツや効果的な学習法についての指導が期待できる学校では、塾講師に匹敵する指導を受けることができます。特に二次試験対策では、教科に精通した教員からのアドバイスが非常に有効であり、質問する姿勢さえあれば塾に通う必要性は低くなります。
志望大学別(国公立vs私立)の塾利用判断
志望大学のタイプによって塾の必要性は大きく異なります。国公立大学と私立大学では入試制度や出題傾向に大きな違いがあり、それに応じた対策が求められます。国公立志望か私立志望かによって塾利用の判断基準が変わることを理解しておくことが重要です。
国公立大学志望の場合、まず共通テスト対策が必要になります。共通テストは高校の学習指導要領に準拠した出題が基本であるため、学校の授業をしっかり理解していれば対応できる部分が多いです。多くの進学校では共通テスト対策の補習や模試を実施しているため、基礎的な対策は学校だけでも可能です。しかし、高得点を狙うためには時間配分や解法テクニックなど、塾ならではの戦略的アプローチが有効になることもあります。
国公立大学の二次試験については、科目数が限られていることが多く、自分の得意科目に集中できるという利点があります。2~3科目に絞って深く学習できるため、独学でも十分に対応できるケースが多いです。特に理系科目は原理原則に基づいた出題が多いため、基礎をしっかり固めれば応用問題にも対応できます。しかし、難関国立大学の場合は高度な思考力を要する問題も多く、そうした問題への対応には専門的な指導が役立つこともあります。
一方、私立大学志望の場合は状況が異なります。私立大学は各校独自の入試形式や出題傾向があり、大学ごとに対策が必要になることが多いです。特に早慶上智など難関私大では、過去の傾向を踏まえた特化した対策が合否を分けることもあります。こうした情報やノウハウは塾や予備校が得意とする分野であり、志望校別の対策講座などを活用することで効率的に準備を進めることができます。
私立大学の英語入試は特に対策が必要です。多くの私立大学では英語の配点比率が高く、長文読解や英作文など、高度な英語力が求められます。学校の授業だけでは対応しきれないレベルの問題も多く、塾の専門的な指導が役立つケースが多いです。特に英作文対策は独学では難しい面があり、添削指導を受けられる環境は大きなメリットになります。
複数の私立大学を受験する場合は、受験日程の組み立てや併願パターンの設計など、戦略的な面でも塾の情報力が役立ちます。私立大学は入試日程が分散しているため、効率的に複数校を受験するためには緻密な計画が必要です。塾や予備校ではこうした受験スケジュールの組み立てについてもアドバイスを受けることができます。
総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜を利用する場合も、塾の専門知識が役立つことがあります。これらの入試では小論文や面接、プレゼンテーションなど、通常の学力試験とは異なる評価方法が用いられることが多く、独自の対策が必要です。塾や予備校では過去の事例を踏まえた実践的な指導が受けられることがあります。
医学部や芸術系など、特殊な入試対策が必要な学部を志望する場合も塾の専門性が重要になります。これらの分野では一般的な受験対策とは異なるアプローチが必要であり、専門的な知識を持つ講師の指導が合否を分けることもあります。そうした専門分野に強い塾や予備校を選ぶことで、効果的な対策が可能になります。
地方在住で都市部の私立大学を志望する場合、地元では入手しにくい情報や対策が必要になることがあります。こうした場合は、オンライン授業を活用するなど、物理的な距離を超えて専門的な指導を受ける方法を検討することも有効です。
志望校のレベルや併願パターンによっても塾の必要性は変わります。難関校一本に絞る場合と、安全策として複数のレベルの大学を受験する場合では対策の幅が異なります。特に私立大学の場合、レベルごとに出題傾向が異なるため、幅広い対策が必要になることがあります。こうした場合は塾の総合的な指導力が役立つことが多いです。
オンライン学習ツールと自習を組み合わせた新しい受験勉強法
インターネットの普及により、従来の「塾に通う・通わない」という二択を超えた新しい受験勉強の形が確立されつつあります。オンライン学習ツールや動画講義など、場所や時間に縛られない学習リソースを活用することで、塾に通わなくても質の高い学習が可能になっています。これらを効果的に組み合わせた「ハイブリッド型」の学習スタイルが注目されています。
YouTube上には質の高い無料講義が多数公開されており、難関大学の受験対策から基礎固めまで、さまざまなレベルの学習コンテンツが提供されています。人気講師の解説動画や解法テクニックなど、従来は塾でしか得られなかった情報にアクセスできるようになり、地方在住者や時間的制約のある生徒にとって大きなメリットとなっています。
有料のオンライン予備校も充実しています。従来の予備校と比較して低コストで質の高い講義を受けられるサービスが増え、自分のペースで学習を進められる利点があります。動画は繰り返し視聴できるため、理解が不十分な部分を何度も復習することが可能です。通学時間がないことで学習時間を確保しやすく、効率的な学習が実現できます。
デジタル問題集や学習管理アプリも日々進化しています。AI技術を活用した問題推薦や弱点分析など、個々の学習状況に合わせたパーソナライズされた学習支援が受けられるツールが増えています。これらを活用することで、独学でも効率的に弱点を克服し、バランスの取れた学力を身につけることが可能になっています。
※効果的なオンライン学習ツールの例
- 大手予備校の動画講義(Z会・河合塾・駿台など)
- スタディサプリなどの月額制オンライン学習サービス
- 過去問解説や受験情報を提供する専門サイト
- AIを活用した学習管理・問題推薦アプリ
- 教科書準拠の学習アプリやデジタル問題集
オンライン学習と学校の授業を組み合わせる方法も効果的です。学校の授業で基礎を固め、オンライン学習で発展的な内容や受験テクニックを学ぶというハイブリッドな学習スタイルを確立することで、塾に通わなくても総合的な受験対策が可能になります。特に進学校の授業内容は高度であることが多いため、それを土台にしてオンライン学習で補完するアプローチは理にかなっています。
質問対応の問題も新しい形で解決されつつあります。オンライン上の質問サービスやSNSの学習コミュニティなど、疑問をリアルタイムで解決できる環境が整ってきています。教員や先輩、同級生との学習グループを作り、LINE等でやり取りする方法も効果的です。こうした相互支援の仕組みを活用することで、塾講師に頼らなくても疑問解決の機会を確保することができます。
モチベーション維持のためのオンラインコミュニティも増えています。同じ目標を持つ受験生同士がオンライン上でつながり、情報交換や励まし合いを行うプラットフォームが登場しています。従来は塾で得られていた「仲間との切磋琢磨」という要素をオンライン上で実現することで、独学の孤独感を軽減することが可能になってきています。
時間管理や学習計画の支援ツールも充実しています。デジタル学習管理ツールやポモドーロタイマーなど、効率的な学習をサポートするアプリケーションを活用することで、自己管理能力を高めることができます。これらのツールは塾のように外部から管理されるのではなく、自律的な学習習慣を育むのに役立ちます。
ただし、オンライン学習には自己管理能力と継続力が不可欠です。情報があふれる環境の中で自分に必要な内容を選別し、計画的に学習を進める力が求められます。この点で不安がある生徒は、完全な独学ではなく、一部塾の機能(例えば月に一度の面談指導など)を取り入れたハイブリッド型の学習スタイルを検討することも一つの選択肢です。
地域や家庭の環境によっても最適な学習スタイルは異なります。地方で塾へのアクセスが限られている場合や、経済的な理由から塾に通えない場合でも、オンライン学習ツールを活用することで質の高い学習環境を整えることが可能になっています。技術の進化により、従来の地理的・経済的制約を超えた学習機会の平等化が進んでいると言えるでしょう。
親と教師が知っておくべき塾なし受験のサポート方法
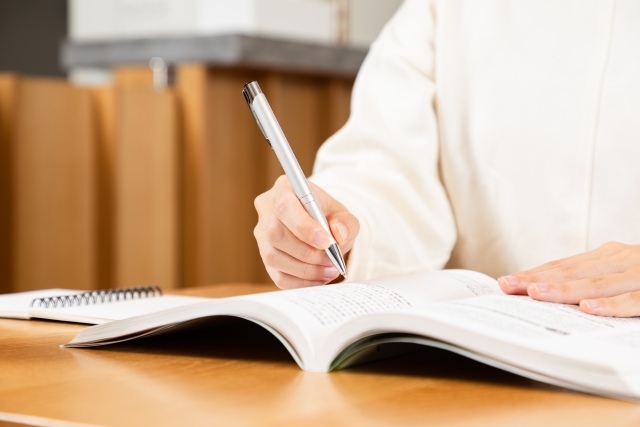
塾なしで受験に挑む生徒を支える親や教師の役割は非常に重要です。適切なサポートがあれば塾に通わなくても十分な受験準備が可能になり、むしろ自立心や学習管理能力など将来にわたって役立つ力を育むことができます。
家庭でのサポートでは勉強に集中できる環境づくりが基本です。静かで適切な照明のある学習スペースの確保や、栄養バランスの取れた食事の提供など、物理的・生理的な側面からの支援が効果的です。精神面でのサポートも重要で、過度なプレッシャーをかけず見守る姿勢や、適切な息抜きの機会を認めることが長期的なモチベーション維持につながります。
学校の教員は塾なし受験生のために補習や個別指導の機会を積極的に設けることで大きな支援になります。特に二次試験対策など専門的な内容については、教科担当者からの直接指導が非常に効果的です。進路指導担当者は最新の入試情報を提供し、志望校選定や出願戦略についてのアドバイスを行うことで、情報面でのサポートが可能です。
費用対効果の観点からは、全科目・全期間の塾通いではなく、弱点科目のみ短期間塾を利用するなど「部分最適」の発想も有効です。また図書館や学校の自習室など無料で利用できる学習環境の活用や、オンライン学習ツールの選別など、限られた予算で最大限の効果を得るための工夫も重要になります。
家庭でできる受験生への効果的な支援策
塾なしで受験に挑む生徒にとって、家庭の支援は非常に重要な要素になります。保護者の適切なサポートがあれば、塾に通わなくても効果的な受験準備が可能になります。家庭でできる支援策には物理的な環境整備から精神的なサポートまで、さまざまな側面があります。
最も基本的なのは学習環境の整備です。静かで集中できる学習スペースの確保や、適切な照明・温度管理など、物理的な環境を整えることが重要です。特に兄弟姉妹がいる家庭では、受験生のための専用スペースを可能な限り確保することが望ましいです。デスクやイス、本棚など必要な家具を揃え、学習に集中できる環境を作ることで、家庭での勉強効率が大幅に向上します。
栄養面でのサポートも重要です。受験生の脳は高度な活動を続けるため、適切な栄養摂取が欠かせません。バランスの取れた食事を規則正しく提供することは、学習効率を高め、体調管理にも役立ちます。特に朝食はその日の学習効率に大きく影響するため、タンパク質や炭水化物をバランス良く含んだ食事を用意することが望ましいです。
生活リズムの管理も保護者が支援できる重要な側面です。適切な睡眠時間の確保や規則正しい生活習慣は、学習効率と体調維持に直結します。特に受験直前期は不安から夜更かしする傾向がありますが、そうした生活リズムの乱れを防ぐためのサポートが必要です。就寝時間の声掛けやスマートフォンの使用制限など、適切な介入が効果的な場合もあります。
精神面でのサポートは特に重要です。受験期は精神的なプレッシャーを感じやすい時期であり、保護者の理解ある態度が大きな支えになります。過度な期待や比較は避け、本人の努力を認め、励ますことがモチベーション維持につながります。時には受験の話題を避け、リラックスできる会話や家族の時間を持つことも大切です。
情報収集の支援も有効です。保護者が大学のオープンキャンパス情報や入試要項、受験に関するニュースなどをチェックし、必要な情報を提供することで、受験生の負担を軽減できます。特に共働き家庭では、こうした情報収集を分担することが受験生にとって大きな助けになります。
適切な教材の選択と購入も重要なサポートです。市販の参考書や問題集は膨大な数があり、どれを選べばよいか迷うことも少なくありません。保護者が学校の先生に相談したり、書店で情報を集めたりして最適な教材を選ぶ手助けをすることで、効率的な学習につながります。必要な教材をためらわずに購入できる経済的なサポートも重要な要素です。
息抜きの機会を認めることも大切です。長期間にわたる受験勉強では、適度な休息と気分転換が必要です。趣味や運動の時間を確保し、リフレッシュできる環境を提供することで、燃え尽き症候群を防ぎ、長期的なモチベーション維持が可能になります。休息も学習の一部と考え、罪悪感なく休める雰囲気づくりが大切です。
家庭学習の習慣づけを支援することも効果的です。「毎日決まった時間に勉強する」という習慣が身につくよう、生活リズムを整えたり、学習時間を家族で尊重したりする姿勢が重要です。特に低学年のうちからこうした習慣を身につけておくことで、受験期の自己管理が格段に容易になります。
モチベーション維持のための工夫も家庭でできる重要なサポートです。目標の視覚化(志望校のポスターを貼るなど)や、小さな目標達成に対する称賛など、モチベーションを高める仕掛けを用意することが効果的です。時には具体的な褒章(好きな食事の提供など)を用意することも、長期的なモチベーション維持に役立ちます。
受験生同士の交流機会を設けることも有効です。同じ目標を持つ友人との勉強会や情報交換の場を提供することで、互いに刺激し合い、モチベーションを高め合うことができます。保護者同士のネットワークを活用して、こうした交流の機会を積極的に作ることも重要なサポートの一つです。
学校の授業を最大限活用するための助言
塾なし受験を成功させるために最も重要なのが、学校の授業を最大限に活用することです。特に進学校では授業内容が高度で充実していることが多く、これを効果的に活用できれば塾に通う必要性は大幅に減少します。授業を活用するための具体的な助言を紹介します。
授業中の集中力を高めることがまず重要です。授業時間内に理解することで家庭学習の効率が格段に上がります。ノートを取る際は単に板書を写すだけでなく、教師の口頭説明も含めて自分の言葉で整理することが大切です。特に重要なポイントや理解が難しい部分はマーカーやふせんを使って視覚的に目立たせるなど、復習しやすい工夫をすることも効果的です。
予習の重要性も見逃せません。授業前に教科書を読み、概要をつかんでおくことで、授業での理解度が大きく変わります。特に数学や理科など積み上げ型の科目では、前回の内容を復習した上で次回の内容に目を通しておくことで、授業での疑問点が明確になり、より効果的に学習を進めることができます。
質問する習慣を身につけることも重要です。わからないことをそのままにせず、積極的に教師に質問することで理解を深めることができます。授業中に質問しにくい場合は、休み時間や放課後に質問する時間を設けましょう。質問は具体的にすることがコツで、「ここがわかりません」ではなく「ここまではわかるのですが、この部分の考え方がわかりません」というように、自分の理解状況を伝えると効果的な回答が得られます。
教師との信頼関係を構築することも大切です。授業に真摯に取り組む姿勢を見せ、積極的に質問や相談をすることで、教師からより丁寧な指導を受けられることがあります。特に受験期には個別のアドバイスや志望校に関する情報提供など、教師からの支援が受けやすくなります。
学校で提供される補習や講習を積極的に活用しましょう。多くの進学校では放課後の補習や長期休暇中の講習が実施されており、これらは塾の授業と同等以上の内容を含むことがあります。特に受験対策に特化した補習は、学校の教師が受験傾向を踏まえて設計していることが多く、非常に効果的です。
模試を活用した学習改善も重要です。学校で実施される模試は単に点数や順位を知るためだけでなく、自分の弱点を発見し、改善するための貴重な機会です。模試後は結果を詳細に分析し、間違えた問題の傾向を把握した上で、弱点を補強する学習計画を立てることが効果的です。
学校の図書館や参考書コーナーを活用することも忘れないでください。多くの学校では受験に役立つ参考書や問題集を揃えており、これらを活用することでコストを抑えながら効果的な学習が可能です。特に過去問題集(赤本)などは高価なため、学校で閲覧できれば大きな助けになります。
同級生との学習グループを作ることも効果的です。同じ志望校や科目に取り組む仲間と定期的に集まり、問題を解き合ったり教え合ったりすることで、理解が深まりモチベーションも維持しやすくなります。特に自分が教える立場になることで、知識の整理や定着が促進されます。
授業ノートの復習と整理を習慣化しましょう。授業で取ったノートは復習の際に重要な資料となります。定期的にノートを見直し、不明点を解消したり、重要ポイントを整理したりすることで、知識の定着度が高まります。特に定期テスト前や模試前には、授業ノートを基にした総復習が効果的です。
授業内容と受験の関連性を常に意識することも大切です。学校の授業は教科書に準拠していますが、その内容は大学入試の基礎となります。「この内容は入試でどのように問われるか」という視点を持ちながら授業を受けることで、受験を意識した効果的な学習が可能になります。授業と入試の橋渡しをする意識が重要です。
費用対効果を考えた受験準備の選択肢
受験勉強には様々な選択肢がありますが、限られた予算で最大の効果を得るためには、費用対効果を考慮した戦略が重要です。塾や予備校は有効な選択肢ですが、コストが高いため、必要な部分だけを上手に活用するという発想が効率的です。費用対効果の高い受験準備の選択肢について詳しく見ていきましょう。
「部分最適」の考え方を取り入れることが重要です。すべての科目を塾に頼るのではなく、特に苦手な科目や対策が必要な科目だけを選んで塾を利用するという方法があります。例えば、数学と英語は塾で学び、その他の科目は学校の授業と自主学習で対応するといった組み合わせが考えられます。これにより費用を抑えながら、必要な部分には専門的な指導を受けることができます。
時期による使い分けも効果的です。高校3年間すべてを塾に通うのではなく、受験直前期だけ集中的に利用するという方法もあります。特に高3の夏以降は受験対策が本格化するため、この時期に絞って塾を活用することで、費用を抑えながら効果的な対策が可能です。部活引退後など、時間的余裕ができた時期に合わせて塾を活用することも一つの戦略です。
集団授業と個別指導の選択も重要です。集団授業は比較的低コストで質の高い講義を受けられる反面、個々の理解度に合わせた指導は難しいという特徴があります。一方、個別指導は高コストながら、自分のペースと理解度に合わせた指導が受けられます。予算と学習スタイルに応じて最適な形態を選ぶことが大切です。
季節講習の活用も費用対効果の高い選択肢です。通年で塾に通わなくても、夏期講習や冬期講習などの季節講習だけを利用することで、集中的に弱点を補強することができます。多くの塾では季節講習は単発で受講可能であり、必要な講座だけを選んで受講することができます。
オンライン学習サービスの活用も有効です。月額制のオンライン予備校やスタディサプリなどのサービスは、従来の塾と比較して低コストで質の高い講義を受けることができます。場所や時間に縛られず自分のペースで学習できる点も大きなメリットです。特に地方在住で近くに適切な塾がない場合は、オンライン学習が強力な選択肢となります。
市販の参考書や問題集の選定にもこだわりましょう。数多くある教材の中から、自分に合った効果的な教材を選ぶことは非常に重要です。教師や先輩のアドバイスを参考にして厳選した教材を徹底的に使い込むことで、低コストでも高い学習効果を得ることができます。買いっぱなしにせず、繰り返し活用することがポイントです。
公共施設の活用も費用対効果を高める方法です。公立図書館や学校の自習室など、無料で利用できる学習環境を積極的に活用することで、追加コストなしで集中できる環境を確保することができます。特に図書館では参考書や過去問題集などが閲覧できることも多く、資料費の節約にもなります。
学習アプリや無料のオンラインリソースも活用しましょう。YouTubeの無料講義や教育系アプリなど、低コストまたは無料で利用できる学習リソースは近年急速に充実しています。こうしたリソースを上手に組み合わせることで、塾に通わなくても質の高い学習が可能になることがあります。
家庭教師については選択肢の一つとして検討する価値があります。塾と比較すると高コストに思えますが、短期間で集中的に弱点を補強するために利用するなら、費用対効果が高い場合もあります。特に大学生のアルバイト家庭教師であれば、比較的リーズナブルな料金で指導を受けることが可能です。
模試については費用対効果を意識して選びましょう。すべての模試を受験するのではなく、志望校や目的に合わせて厳選した模試だけを受けることで、コストを抑えながら必要な情報を得ることができます。特に志望校別の模試は、その大学に特化した情報が得られるため、費用対効果が高いと言えます。
最後に、進路指導や就職支援など、学校が無料で提供しているサービスを積極的に活用することも大切です。多くの高校では進路指導部が大学の情報提供や出願サポートを行っており、これらを活用することで追加費用なしで必要な支援を受けることができます。教育相談やカウンセリングなど、メンタル面のサポートも活用できる場合があります。
